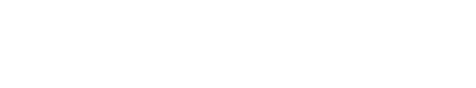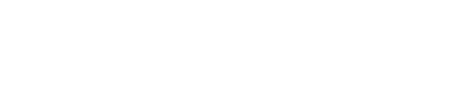2025/03/14
36協定をしていても違法な残業(時間外労働)になる4つのケース
「うちの会社は36協定を結んでいるから、残業は問題ない」と思っていませんか?
派遣社員として働いていると、派遣先の業務状況に応じて残業を求められることがあるでしょう。
しかし、36協定があるからといって、すべての残業が合法というわけではありません。実は、36協定が締結されていても、一定の条件を満たさない場合は「違法な残業」となってしまうケースがあるのです。
違法な残業が続けば、心身への負担が増すだけでなく、未払いの割増賃金が発生する可能性もあります。また、派遣社員の場合、派遣元(派遣会社)と派遣先(勤務先企業)の関係を正しく理解しておくことが、自分の働き方を守るために重要です。
本記事では、36協定を締結していても違法となる4つのケースについて詳しく解説し、派遣社員として知っておくべきポイントを紹介します。
「もしかして自分の残業は違法かも?」と思ったら、ぜひ最後までチェックしてください。
1. 派遣元の36協定の範囲を超えた残業
派遣社員の時間外労働について考える際、重要なのは適用される36協定は「派遣先」ではなく「派遣元(派遣会社)」のものだという点です。
1-1.36協定は派遣元のものが適用される
派遣社員は派遣先の企業で働いていますが、雇用契約を結んでいるのは派遣元(派遣会社)です。そのため、労働時間や時間外労働に関するルールは、派遣元が締結している36協定に基づいて決まります。
例えば、派遣先が「毎月45時間まで残業OK」という36協定を結んでいたとしても、派遣元の36協定が「毎月30時間まで」となっていた場合、30時間を超える残業は違法となります。
1-2.派遣先の指示でも違法な残業になるケース
派遣先の上司から「今日は業務が立て込んでいるから2時間残業して」と言われることがあるかもしれません。
しかし、派遣元の36協定の範囲を超える残業は認められないため、派遣先の指示であっても違法な残業になってしまう可能性があります。
特に、以下のようなケースは注意が必要です。
- 派遣元が許可していないのに、派遣先の指示で残業を行う
- 派遣元の36協定の上限を超えている
- 特別条項付き36協定があっても、その上限を超えている
1-3.派遣元の36協定を確認する方法
「自分の派遣元はどんな36協定を結んでいるのか?」を知ることは、違法な残業を避けるために重要です。確認する方法として、以下の手順を試してみましょう。
|
(1)派遣会社の担当者に直接聞く 「派遣社員としての時間外労働の上限はどのように定められていますか?」と確認するとよいでしょう。
(2)労働条件通知書や雇用契約書を確認する 労働条件通知書や雇用契約書には、時間外労働の有無や上限時間について記載されていることがあります。
(3)労働組合や労働基準監督署に相談する 派遣会社が明確に答えてくれない場合は、労働組合や労基署に相談するのも手段の一つです。 |
派遣社員の残業は、派遣先のルールではなく、派遣元のルールに従うという点をしっかり理解し、違法な残業を避けるようにしましょう。

2. 労働者代表の選出が不適切な場合
36協定を締結するためには、「労働者の過半数代表」と呼ばれる人が、会社(使用者)と協定を結ぶ必要があります。
しかし、この労働者代表が適切に選出されていない場合、協定自体が無効となり、時間外労働が違法となる可能性があります。
2-1.労働者代表とは?
労働者代表とは、会社側ではなく労働者側の立場で、36協定の締結や労働環境に関する交渉を行う人のことです。派遣社員を含むすべての労働者の代表として、労使協定を結ぶ役割を担います。
ただし、この代表が適切に選ばれていなかった場合、その36協定は無効となり、協定に基づく時間外労働はすべて違法なものになってしまいます。
2-2.不適切な労働者代表の選出例
以下のようなケースでは、労働者代表が適切に選出されていない可能性が高く、36協定の効力が疑われます。
◆会社が勝手に代表を指名した
本来、労働者代表は労働者の「投票」「挙手」「話し合い」などの民主的な手続きによって選ばれる必要があります。しかし、会社側が一方的に代表者を指名してしまうと、その協定は無効になる可能性があります。
(例)
✖ 会社「この人が労働者代表です。話し合いは特にしません。」
✔ 正しい選び方 → 労働者全体で話し合い、投票などで決定する
◆会社の意向を優先する人が代表になっている
労働者代表は、労働者の立場で会社と交渉する役割を持っています。しかし、経営陣や管理職に近い人が代表になっていると、会社寄りの判断をしてしまい、実質的な交渉が行われない可能性があります。
(例)
✖ 「会社に逆らえないから、言われるがままに36協定にサインした」
✔ 正しい選び方 → 労働者が意見を言いやすい人が代表になる
◆ 派遣社員が代表選出に参加できていない
派遣社員も労働者の一員であり、36協定に影響を受けます。しかし、代表選出の過程で派遣社員が除外されていると、適正な協定とは言えません。
(例)
✖ 正社員だけで代表を決め、派遣社員に通知すらない
✔ 正しい選び方 → 派遣社員も含めて選出に関与する
2-3.適切な労働者代表が選ばれているか確認する方法
◆代表者がどのように選ばれたかを確認する
「代表はどうやって決められましたか?」と会社に確認しましょう。
労働者全体の意見が反映されていなかった場合、無効となる可能性があります。
◆36協定の内容を確認する
労働者代表の名前が記載されているかチェックし、不明点があれば説明を求めましょう。
派遣社員が適切に関与できているかを確認する
派遣社員も労働者代表の選出に関与する権利があります。自分たちの意見が反映されているかを確認しましょう。
2-4.労働者代表が不適切だとどうなる?
労働者代表が不適切な方法で選ばれていた場合、その36協定は無効となり、本来認められるはずの時間外労働の上限や特別条項も適用されなくなります。つまり、36協定に基づく残業そのものが違法になるのです。
派遣社員として働く際も、会社の36協定の成り立ちや代表の選出方法を確認し、自分の労働環境が適正かどうかをチェックすることが重要です。

3. 36協定に定められた具体的事由に該当しない残業
36協定には、時間外労働を行う「具体的な事由」を記載する必要があります。これは「どんな理由なら残業をさせてもよいか?」を明確にするためのものです。
もし、36協定に書かれていない理由での残業が発生している場合、その残業は違法となる可能性があります。派遣社員として働く場合も、業務が36協定の条件を満たしているかどうかを意識することが大切です。
3-1.36協定に書かれている「具体的な事由」とは?
36協定には、企業が時間外労働を命じる際の「正当な理由」を明記する必要があります。例えば、以下のような内容です。
- 納期が逼迫しており、どうしても対応が必要な場合
- 緊急のトラブル対応が発生し、通常業務では処理しきれない場合
- 繁忙期における特別な業務対応
このようなケースであれば、36協定に基づいた時間外労働が可能になります。
しかし、「何となく忙しいから」「人手が足りないから」などの曖昧な理由では、協定違反となる可能性が高いのです。
3-2.36協定の事由に当てはまらない違法な残業の例
✖「毎日恒常的に残業が発生している」
本来、時間外労働は「一時的・例外的なもの」であるべきです。にもかかわらず、毎日のように定時後の残業が当たり前になっている場合、36協定の趣旨から逸脱している可能性があります。
✖ 「派遣先の都合で急に長時間の残業を命じられた」
派遣社員の場合、派遣元が定める36協定のルールに従う必要があります。にもかかわらず、派遣先の都合で勝手に長時間の残業を指示されるのは違法です。
✖「理由もなくとりあえず残業をさせられる」
上司から「今日も残業よろしく」と言われるが、業務に特別な理由がない場合、36協定の「具体的な事由」に該当しない可能性があります。
3-3.派遣社員が確認すべきポイント
派遣社員として違法な残業を防ぐためには、以下のポイントを確認しておきましょう。
- 36協定の内容を確認する
- 派遣元(派遣会社)の36協定にはどのような事由が記載されているか?
- その範囲を超える残業をしていないか?
- 派遣先の指示で勝手に残業をしない
派遣社員の時間外労働は、派遣元の許可が必要です。派遣先が指示したとしても、勝手に残業を行うのは避けましょう。
「忙しいから」という理由だけで恒常的に残業していないかをよく考え、「この残業は適法か?」「派遣元の36協定の範囲内か?」と自分で考える習慣を持ちましょう。
3-3.36協定に違反する残業を命じられたら?
もしも、36協定の事由に該当しない違法な残業を命じられた場合、派遣社員としてできる対応を知っておくことが大切です。
- 派遣元に相談する(「派遣先で不適切な残業を指示された」と報告する)
- 労働基準監督署や労働組合に相談する(状況を説明し、対応策を考える)
- 記録を取る(指示された時間や内容をメモし、後から証拠として活用できるようにする)
派遣社員として「派遣先の指示=すべて従わなければならない」と思い込まず、36協定のルールを理解して、自分の労働環境を守る意識を持つことが重要です。

4. 適切な割増賃金の未払い
時間外労働(残業)には、法律で定められた割増賃金(残業代)が支払われる必要があります。
しかし、36協定が締結されていても、適切な割増賃金が支払われていなければ違法です。
派遣社員の場合、残業代の支払いは「派遣元(派遣会社)」が行うため、「派遣先で残業したのに正しく支払われない」という問題が発生しやすい点に注意しましょう。
4-1.残業代の基本ルール(派遣社員も適用)
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働には、割増賃金を支払う義務があります。
|
割増賃金の計算ルール 法定労働時間(8時間/日・40時間/週)を超える残業:25%以上 月60時間を超える残業(大企業のみ):50%以上 休日労働(法定休日):35%以上 深夜労働(22時~翌5時):25%以上 |
派遣社員もこのルールに従い、適切な残業代を受け取る権利があります。
4-2.こんな未払いケースは違法!
派遣社員の現場では、次のようなケースで違法な未払い残業が発生することがあります。
◆「みなし残業」の範囲を超えている
派遣先によっては、「みなし残業制度(固定残業代)」が適用されている場合があります。これは、あらかじめ一定時間分の残業代を基本給に含めて支払う制度ですが、その時間を超えた分は、別途残業代が支払われる必要があるのです。
(例)
✖ 派遣元:「みなし残業20時間分が含まれているので、それ以上の残業代は出ません」
✔ 正しくは → 20時間を超えた分の残業代は追加で支払われるべき
◆サービス残業の強要
派遣先で「業務の一環だから」と言われて、タイムカードを押した後に働かされることはありませんか?これは典型的なサービス残業であり、未払い残業の違法行為に当たります。
(例)
✖ 上司:「少しだけだから、タイムカードを押した後に手伝って」
✔ 正しくは → 労働時間としてカウントし、残業代を支払うべき
◆ 派遣先の指示で残業したのに、派遣元が認めない
派遣社員は、派遣元の指示なしに派遣先で勝手に残業することができません。しかし、派遣先の指示で残業をしてしまった場合、派遣元が「指示していないから支払えない」と対応するケースもあります。
(例)
✖ 派遣元:「派遣先で勝手に残業したなら、うちは払えません」
✔ 正しくは → 派遣先と調整し、適切な残業代を支払うべき
4-3.派遣社員が未払い残業を防ぐための対策
派遣社員は、派遣元と派遣先の間に挟まれる立場なので、未払い残業が起こりやすいです。自分の権利を守るために、以下のポイントを意識しましょう。
◆残業の許可を必ず派遣元に取る
派遣先で残業を求められたら、「派遣元に確認する必要があります」と伝えましょう。
派遣元の許可を得ずに残業すると、後で残業代をもらえない可能性があります。
◆タイムカードや業務記録を取る
勤務時間を記録し、実際に働いた時間が適切にカウントされているか確認しましょう。
タイムカードの記録と実際の労働時間が違う場合、未払いの証拠となります。
派遣元に相談し、それでも対応しない場合は労基署へ報告しましょう。
派遣元が適切に対応してくれない場合、労働基準監督署や派遣社員向けの相談窓口に相談することも選択肢です。
4-4.未払い残業のトラブルは早めに対処を!
「なんとなくおかしい」と感じたら、そのままにせず、派遣元や専門機関に相談しましょう。未払い残業を放置すると、働いた分の給与がもらえないだけでなく、慢性的な違法残業の温床になってしまいます。

5.まとめ 〜36協定があっても違法な残業は存在する?!〜
派遣社員として働く上で、「36協定があるから大丈夫」と思い込むのは危険です。
今回紹介した4つのケースのように、36協定があっても違法な残業は発生することがあります。
残業代が支払われない、みなし残業の範囲を超えている、サービス残業が発生している場合は違法なので、以下の方法で派遣社員としての対策しましょう。
✓派遣元の36協定を確認する
✓ 派遣先の指示だけで残業しない(必ず派遣元の許可を取る)
✓ 勤務時間をしっかり記録する(未払い対策のため)
✓違法な残業が疑われる場合は、派遣元や労働基準監督署に相談する
自分の労働環境を守るために、知識を身につけて正しく対応することが大切です。
お仕事情報のおすすめ記事
-
2025/08/15
信頼を築く!明日から実践できるビジネスマナーの基本
-
2023/02/10
あなたの日常生活を支えるお仕事! 金属加工の仕事内容って?
-
2023/02/24
健康を支える大事な仕事 医療製造の仕事とは?
-
2023/04/28
女性活躍!!品質検査のお仕事とは?