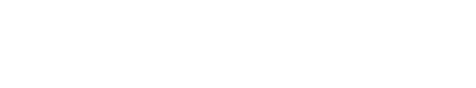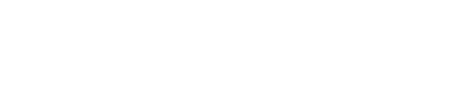2025/04/18
派遣契約の流れを3つのステップで徹底解説
「派遣契約ってどう進めればいいの?」
――繁忙期を控え、上司から急遽の人員増強を指示されたものの、派遣社員を受け入れる契約手続きの流れがわからず戸惑っている担当者の方も多いのではないでしょうか。
派遣契約には、派遣会社への依頼から契約締結、そして派遣スタッフの受け入れ開始まで、押さえるべき3つのステップがあります。
本記事では、派遣契約の流れを3つのステップに分けて丁寧に解説します。
初めて派遣契約を扱う担当者の方でも安心して進められるよう、各ステップごとに具体的な手続き内容と法的根拠(労働者派遣法など)をわかりやすく説明します。
派遣契約で起こりがちなトラブルや企業側の注意点も交えていますので、ぜひ派遣社員受け入れの参考にしてください。派遣社員を上手に活用すれば、必要な時に必要なスキルを持つ人材を必要な期間だけ確保できる柔軟なサービスです。
それでは、さっそく派遣契約のステップを見ていきましょう。
1. 派遣会社への依頼と事前準備(STEP1)
まずは、人材派遣会社に派遣スタッフの紹介を依頼する段階です。派遣会社へ問い合わせる前に、自社で受け入れたい人材の条件を整理しておきましょう。
具体的には、担当させたい業務の内容、必要なスキルや経験、派遣期間(開始日と終了日)、希望する就業開始日、募集人数、就業場所や勤務時間・休日などの就業条件を社内で確認します。
これらの情報を明確にしておくことで、派遣会社とのヒアリングがスムーズになり、ミスマッチを防ぐことにつながります。
1-1.派遣会社へのヒアリング対応
派遣会社に問い合わせをすると、担当者との打ち合わせ(ヒアリング)が行われます。
派遣会社は企業のニーズに合った人材を選定するため、細かな要件を確認してきますので、できるだけ詳細に回答しましょう。
業務内容や求める人物像はもちろん、派遣を利用する背景や目的も共有すると、派遣会社側で適切な人選がしやすくなります。十分な情報提供は、派遣スタッフ決定後のミスマッチ防止に役立ちます。
1-2.職場見学の実施:
必要に応じて、派遣スタッフ候補者による職場見学が行われる場合があります。
職場見学とは、実際に派遣予定のスタッフが就業前に職場を訪問し、業務内容や職場環境を事前に確認する機会です。質疑応答の場を設けて仕事内容への理解を深めてもらうことで、安心して就業開始してもらえるでしょう。
ただし、注意点としてこの職場見学は面接ではありません。後述するように、派遣先企業(受け入れ企業)が派遣スタッフを特定する目的での面接や選考行為は法律で禁止されています。
1-3.派遣先による選考行為の禁止
人材派遣では、派遣スタッフは派遣元である派遣会社と雇用契約を結んでおり、派遣先企業と派遣スタッフの間に直接の雇用関係はありません。
そのため、派遣先企業が派遣スタッフの採用面接を行ったり、履歴書を直接要求したりといった特定行為(労働者を特定する行為)はできない決まりになっています(労働者派遣法第26条第6項)。
これは派遣労働者の公平な就業機会を守るための規制であり、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先による事前面接などは一切行えません。例えば試験を課したり書類選考をすることも禁止です。
派遣スタッフの選定は派遣会社が行い、派遣先企業は提示された候補者の中から受け入れるかを判断する流れになります。うっかり面接のような行為をしてしまうと労働者派遣法違反となるおそれがあるため十分注意しましょう。
1-4.抵触日の通知
派遣契約を依頼する段階で、抵触日についても確認が必要です。
抵触日とは、その派遣スタッフの受け入れ期間が法定の上限(原則3年)に達し、以降は派遣受け入れができなくなる最初の日を指します 。
労働者派遣法の2015年改正により、派遣先が同じ部署で派遣社員を受け入れられる期間は原則3年までと定められました (無期雇用の派遣社員や60歳以上の方など一部の例外あり)。
例えば、2021年10月1日に初めて派遣スタッフを受け入れた場合、3年後の2024年10月1日が抵触日となります。
派遣先企業は派遣契約締結にあたり、この抵触日を派遣会社に通知する義務があります。期間制限を超えて派遣を継続すると違法状態となり、行政指導や是正勧告の対象となりますので、契約開始前に抵触日を把握して派遣会社と共有しておきましょう。
1-5.その他の注意点(派遣できない業務など)
依頼内容を検討する際には、その業務が派遣契約で対応可能かも確認しましょう。労働者派遣法では派遣が禁止されている業種・業務があり、例えば港湾運送業、建設業、警備業、医療関係などは派遣労働者を受け入れることができません (これらは禁止業務と呼ばれます)。
もし依頼しようとしている職種が該当する場合は、派遣ではなく請負契約や直接雇用など別の手段を検討する必要があります。
以上がSTEP1の準備段階です。事前準備と派遣会社との綿密なすり合わせを経て、ニーズに合った派遣スタッフ候補の提案へと進みます。それでは次に、実際の契約手続きと派遣スタッフ決定のステップを見てみましょう。

2. 派遣契約の締結と派遣スタッフの決定(STEP2)
派遣する人材の候補が決まったら、派遣会社と受け入れ企業との間で契約を締結します。
派遣契約の手続きは大きく二段階に分かれます。まず一つ目が基本契約(労働者派遣基本契約)の締結、次に派遣ごとの個別契約(労働者派遣契約)の締結です。
初めてその派遣会社から派遣スタッフを受け入れる場合には、まず基本契約を結び、続いて個別契約を取り交わす流れになります。
2-1.労働者派遣基本契約の締結
基本契約書とは、今後その派遣会社との間で締結する個々の派遣契約に共通する前提条件を定めた包括的な契約です。
例えば、派遣料金の支払い条件(支払サイトや請求方法)、機密保持義務、万が一トラブルが起きた場合の損害賠償責任の所在など、個別契約に共通する取り決めを定めます 。
基本契約は一度結べば、その後同じ派遣会社から繰り返しスタッフを受け入れる際に改めて結ぶ必要はなく、必要に応じて内容の見直しを行っていきます。
2-2.労働者派遣契約(個別契約)の締結
基本契約を交わした後、実際に派遣スタッフを受け入れるごとに個別の派遣契約書を締結します。
個別契約書には、派遣する人ごとの具体的な契約条件を明記します。例えば、派遣期間(就業開始日と終了予定日)、就業日と就業時間、業務内容・担当職務、派遣人数、派遣料金(時給や月額など)や契約更新の有無など、派遣スタッフごとに定めるべき事項が記載されます 。
これらは労働者派遣法施行規則によって必ず記載すべき項目が定められており、契約書面として双方で取り交わします。
2-3.契約書に盛り込まれる項目と法定事項
個別契約書を取り交わす際には、労働者派遣法で定められた事項を正確に盛り込む必要があります。例えば、「派遣先責任者」の氏名や連絡先もその一つです。派遣先責任者とは、派遣先(受け入れ企業)で派遣スタッフの受け入れ管理を統括する責任者であり、派遣先は就業場所ごとに選任・配置が義務付けられています 。
契約書には派遣先責任者を含め、派遣先で指揮命令を行う担当者(指揮命令者)や苦情を受け付ける担当者(苦情申出先)の氏名も記載します 。
これらの役割を事前に自社内で決めておき、契約書に正しく反映させましょう。特に派遣先責任者を選任しなかった場合は労働者派遣法違反となり、30万円以下の罰金が科される可能性もあります。
派遣スタッフを受け入れる企業として、コンプライアンスの観点からも確実に選任・周知しておくことが重要です。
2-4.派遣先管理台帳の作成:
派遣契約の締結と同時に、受け入れ企業側で派遣先管理台帳を作成することも忘れてはなりません。
派遣先管理台帳とは、派遣先企業が必ず作成しなければならない台帳で、派遣スタッフごとの就業実績や契約内容を記録したものです(労働者派遣法第42条)。派遣スタッフの氏名、就業日・時間、業務内容などを記載し、派遣契約終了日から3年間保存する義務があります。
台帳を整備することで派遣スタッフの勤務状況を適切に把握でき、法令遵守にもつながります。なお、台帳の書式は派遣会社が用意してくれる場合もありますので、必要に応じて相談すると良いでしょう。
2-5.派遣スタッフの決定
契約書類の取り交わしが完了すると、いよいよ派遣してもらうスタッフが正式に決定します。
派遣会社から企業の要望に合った人材が提示されますので、その方を受け入れることで合意すれば就業開始の調整に入ります 。もし契約内容に変更や追加の希望がある場合は、必ず派遣会社を通じて契約書を修正しましょう。
契約外の業務を現場で指示したり、契約期間を過ぎても継続就業させてしまうとトラブルの原因となるため注意が必要です。

3. 派遣スタッフの就業開始と受け入れ準備(STEP3)
契約手続きがすべて完了すると、いよいよ派遣スタッフが実際に就業を開始します。
派遣社員の初出勤日までに、受け入れ企業側で万全の受け入れ準備を整えておくことが大切です。
自社の社員も派遣スタッフもお互いスムーズに仕事を始められるよう、以下のような準備・対応を行いましょう。
3-1.社内周知
派遣スタッフを受け入れる旨を関係部署や社員に事前に周知します。新しいスタッフが来ることをチームメンバーに知らせ、受け入れ態勢を共有しましょう。
3-2.入館証やIDカードの発行
派遣スタッフが社屋に出入りできるよう、社員証やセキュリティカードを用意します。
設備・備品の準備: 派遣スタッフが使用するデスクやパソコン、電話、文具など必要な備品を事前に準備し、すぐ使える状態にセットアップしておきます。
3-3.システム利用手続き
社内ネットワークや業務システムのアカウント発行など、IT環境の利用手続きを済ませておきます。
業務マニュアルや引継ぎ資料の用意: 担当してもらう業務について、マニュアルや引継ぎノートがあれば準備しておきます。初日にスムーズに業務説明ができるよう資料を整えましょう。
3-4.指揮命令系統の明確化:
派遣スタッフに業務指示を出す担当者(指揮命令者)や報告ラインを社内で確認し、関係者全員で共有します。誰が日々の指示を行うのかを明確に伝えておくことで、派遣スタッフも安心して業務に取り組めます。
また、就業初日には派遣スタッフの緊張を和らげ、円滑に馴染んでもらう工夫をしましょう。初日の朝には職場のメンバーへの紹介を行い、オフィス内の設備(給湯室やロッカー、休憩スペース等)の案内をします。就業規則や社内ルール、タイムカードの打刻方法やセキュリティルール、緊急時の連絡フローなども説明しておくと親切です。
こうした受け入れ時のサポートを丁寧に行うことで、派遣スタッフが安心して業務を開始でき、その後の生産性向上にもつながるでしょう
就業開始後も、派遣スタッフが働きやすい環境を維持することが企業側の責任です。
定期的に派遣スタッフ本人とコミュニケーションを取り、業務の進捗や困りごとがないか確認しましょう。
万一、労務管理上の問題(残業の増加やハラスメントの訴えなど)が発生した場合は、派遣元企業とも速やかに連携し、適切に対処することが重要です。
派遣契約の期間が満了に近づいたら、更新手続きや終了時のフォローも忘れずに行います。契約を更新する場合は派遣会社との間で所定の手続きを踏み、更新契約書を締結しましょう。
更新しない場合も契約で定められた終了手続きを遵守し、必要に応じて派遣スタッフの引継ぎや他の就業先の調整について派遣会社と協議してください。

おわりに:派遣契約は適切な手続きと準備がカギ
派遣契約の流れを3つのステップに分けて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
初めてでもポイントを押さえれば難しいものではありません。派遣契約では事前準備から契約手続き、受け入れ準備まで一つひとつ丁寧に対応することが大切です。
派遣社員受け入れの際には、業務内容や期間、就業条件などをしっかり派遣会社と共有し、必要な契約書類を法令に沿って締結しましょう。契約後は万全の受け入れ態勢を整えることで、派遣スタッフもスムーズに戦力として活躍してくれるはずです。
自社に派遣社員を受け入れるのが初めてで不安な場合でも、信頼できる派遣会社であれば契約手続きから就業後のフォローまで丁寧にサポートしてくれます。
本記事を参考に派遣契約の全体像を把握し、不明点は派遣会社に確認しながら進めてみてください。
まずはお気軽にご相談ください。
派遣契約や人材活用について疑問や不安がありましたら、ぜひお問い合わせください。適切な人材活用を通じて、貴社の課題解決をサポートいたします。  お電話でのご相談:0120‐085‐075
お電話でのご相談:0120‐085‐075
お仕事情報のおすすめ記事
-
2025/08/15
信頼を築く!明日から実践できるビジネスマナーの基本
-
2023/02/10
あなたの日常生活を支えるお仕事! 金属加工の仕事内容って?
-
2023/02/24
健康を支える大事な仕事 医療製造の仕事とは?
-
2023/04/28
女性活躍!!品質検査のお仕事とは?