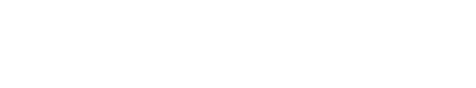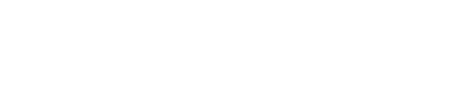2025/04/11
派遣の抵触日とは?種類や派遣先企業の注意点について
派遣社員を活用している企業の多くが、ある日突然「抵触日」という言葉に直面し、驚くことがあります。
「今の派遣社員はとても優秀だし、契約を延長したい。でも法律で制限があるらしい…」
「抵触日って何?どうすれば違反にならないの?」
こうした疑問や不安は、派遣という仕組みが「便利」な一方で、「法律に基づいて運用される制度」であることに起因します。
とくに2015年と2020年の労働者派遣法改正をきっかけに、派遣社員の受け入れ期間に関するルールが明確化・厳格化されました。
本記事では、「抵触日」とは何か、その種類や派遣先企業としての注意点、違反時のリスク、さらに「どうすれば今後も派遣社員を活用し続けられるのか」について、詳しく・わかりやすく解説します。
1. 抵触日とは?派遣先企業が必ず知っておくべき基礎知識
「抵触日(ていしょくび)」とは、派遣社員の受け入れに関して法律で定められた「受け入れ可能な期間の起点日」のことです。
労働者派遣法では、派遣社員を同じ部署で継続して受け入れられる期間に制限があり、原則として「3年以内」と定められています。
この「3年以内」という期間のスタート地点が「抵触日」なのです。
つまり、抵触日を正しく把握していなければ、「気づかぬうちに期間制限を超えてしまい、法律違反になる」という事態も起こり得ます。
2. 抵触日には2種類ある:事業所単位と個人単位の違い
派遣の抵触日には、「事業所単位の抵触日」と「個人単位の抵触日」の2つがあります。
この2つの違いを理解しておくことが、違反を防ぐ第一歩です。
(1)事業所単位の抵触日
派遣先企業の「部署単位(課やチームなど)」で考える受け入れ制限です。
同じ部署に複数の派遣社員を受け入れている場合、最初に受け入れた日から3年が経過すると、原則としてそれ以上の派遣受け入れはできません。
(2)個人単位の抵触日
同じ派遣社員個人が、同じ部署で継続して働けるのは原則3年までと定められています。
たとえば、優秀なAさんを3年以上同じ課で働かせたいと思っても、法律上は制限があるのです。
これらの制限により、派遣社員の受け入れは一時的な活用に限定され、正社員や直接雇用への切り替えを促すことが法律の趣旨とされています。

3. 抵触日を超えてしまった場合のリスクと対応策
抵触日を過ぎた後も派遣社員を同じ部署で受け入れ続けると、労働者派遣法違反に該当します。
このような違反が判明した場合、厚生労働省からの指導、是正勧告、場合によっては行政処分の対象となることがあります。
とくに、「実質的には同じ業務を継続させているのに、部署名や業務内容を名目だけ変更して継続」している場合、監査で発覚すれば重大なコンプライアンス違反とみなされます。
【抵触日が過ぎてしまった場合の対応策】
・ 抵触日が近づいてきた場合は、早めに派遣会社と相談し、切り替えの方法を検討することが大切です。
・ たとえば、「直接雇用への転換」「配置転換(実質的な業務変更を伴う)」「派遣から紹介予定派遣への切り替え」などが選択肢となります。
4. よくある誤解とその注意点
派遣契約に関する制度は複雑であるため、現場で以下のような誤解が生じることがあります。
・ 派遣会社を変更すれば、抵触日はリセットされるのでは?
→ いいえ。派遣会社を変更しても「同じ人が同じ部署で働く場合」は個人単位の抵触日はそのまま継続します。
・ 一度契約を終了して数週間空ければ、またゼロからカウントされる?
→ 中断期間が1ヶ月未満の場合、連続勤務と見なされ、カウントは継続されます。形式上の空白では無効です。
・ 部署名を変更すれば別部署とみなされる?
→ 実質的に同じ業務・同じ人間関係であれば「同一部署」とされ、法的には回避になりません。
5. 派遣社員の受け入れを継続したい場合の選択肢
派遣社員を今後も活用したいと考える企業様にとって、抵触日制度は大きなハードルに感じるかもしれません。
しかし、制度を理解したうえで適切な対策をとれば、今後も有効に人材を活用することが可能です。
【主な対応手段】
① 紹介予定派遣への切り替え:
一定期間の派遣就業後に直接雇用に移行する前提の制度です。3年ルールを回避しながらミスマッチも防げます。
② 直接雇用の検討:
優秀な派遣社員を正社員・契約社員として登用することで、即戦力を継続して活かすことができます。
③ 部署の異動:
配置転換を行うことで、個人単位の抵触日をリセットできます。ただし実態の業務内容が異なることが必要です。

6. 法改正の経緯と現在の制度の背景
2015年の労働者派遣法改正により、従来の「業務単位による派遣期間制限」は廃止され、「事業所単位」と「個人単位」での制限に再構成されました。
これにより、すべての業務において原則3年という期間制限が適用されるようになりました。
また、2020年には「同一労働同一賃金」の原則が強化され、派遣社員と正社員との待遇差の是正が求められるようになっています。
これらの法改正の背景には、派遣労働者の安定した雇用確保とキャリア形成支援という目的があります。
7. まとめ 派遣社員の活用は「制度を理解すれば」もっと自由にできる
抵触日は、派遣社員の受け入れを制限するルールですが、必ずしも「3年で終わり」という話ではありません。
正しい知識と計画的な運用をすれば、引き続き派遣制度を活用することが可能です。
「抵触日が近づいてきた」「今の人材を手放したくない」「派遣か紹介か、最適な手段が分からない」——
そんなときは、私たち専門の人材サービス会社にご相談ください。
お客様の事業や組織体制に応じて、柔軟かつ合法的な対応策をご提案いたします。
現在ご契約中の派遣社員についてのご相談、抵触日を踏まえた今後の人材活用戦略、紹介予定派遣や直接雇用のご相談など、幅広く対応しております。
お電話でのご相談:0120‐085‐075
お仕事情報のおすすめ記事
-
2025/08/15
信頼を築く!明日から実践できるビジネスマナーの基本
-
2023/02/10
あなたの日常生活を支えるお仕事! 金属加工の仕事内容って?
-
2023/02/24
健康を支える大事な仕事 医療製造の仕事とは?
-
2023/04/28
女性活躍!!品質検査のお仕事とは?