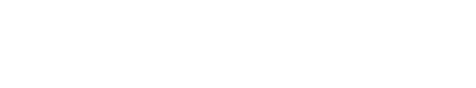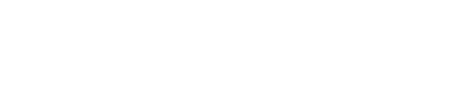2025/04/25
派遣社員にさせてはいけない6つの業務としてはいけない指示
「これって派遣スタッフにお願いしても大丈夫?」
現場でよく聞かれるこの疑問。
実は、派遣社員に任せてはいけない業務や、してはいけない指示には、労働者派遣法などの法律で明確なルールが定められています。
に違反してしまえば、企業の信頼や生産性を損なうだけでなく、法的リスクにもつながりかねません。
このブログでは、派遣社員に任せてはいけない業務やNG指示の具体例をわかりやすく解説。法令遵守を徹底しながら、安心して派遣スタッフと協力して働くためのポイントをお伝えします。
1.派遣の基本ルールとは?
企業が人手不足を補う手段として多く活用されている「派遣社員」ですが、正社員やアルバイトと同じ感覚で業務を依頼してしまうと、思わぬ法的トラブルに発展することがあります。まずは、派遣社員の仕組みと、守るべき基本ルールについて整理しておきましょう。
1-1.派遣と請負・業務委託の違い
派遣とよく混同されるのが「請負」や「業務委託」という働き方です。これらは一見すると似ていますが、労働法上の位置づけがまったく異なります。
派遣:派遣元(派遣会社)と雇用契約を結んだ労働者が、派遣先企業の指揮命令を受けて働く形態。
請負・業務委託:業務を受託した業者が、自らの裁量で業務を遂行する。発注者(依頼元)は直接の指揮命令を行わない。
この「指揮命令権の有無」が最大の違いです。派遣では、現場で実際に指示を出すのは派遣先企業になりますが、雇用主はあくまで派遣元であることを忘れてはいけません。
1-2.指揮命令権の原則
労働者派遣法により、派遣先企業は「指揮命令者」を明確に定める必要があります。これは、派遣社員が誰の指示で動くのかをはっきりさせることで、不当な扱いを防ぐためです。
ただし、この「指揮命令権」には注意点があります。たとえば、契約にない業務を新たに指示したり、派遣社員に他の社員を管理させるような行為は、法律に違反する可能性があります。
1-3.受け入れ企業と派遣元の役割分担
派遣社員に関する責任や業務管理には、派遣元と派遣先の明確な分担があります。
| 派遣元の役割 | 派遣先の役割 | |
| 雇用契約 | 結ぶ | 結ばない |
| 給与の支払い | 実施する | 実施しない |
| 業務の指示 | しない | 実施する(契約範囲内) |
| 労働時間管理 | 基本的には派遣先の管理下 | 実施する |
これらのルールを守らずに指示を出したり、業務を任せたりすると、最悪の場合、派遣契約の違法性を問われるケースもあります。

2.派遣社員に任せてはいけない6つの業務
派遣社員に業務を任せる際は、「できる業務」と「してはいけない業務」を明確に理解しておくことが不可欠です。法律で派遣が禁止されている業務もあり、違反すると企業側が罰則を受けることになります。この章では、労働者派遣法で禁止されている6つの業務について、具体例を交えて解説します。
2ー1. 警備業務
禁止理由: 警備業法により、警備業務は請負契約でなければならないと定められています。そのため、派遣という形態では行えません。
【 該当例 】
ビルや施設の常駐警備
イベント会場の入退場管理
駐車場の誘導や監視
2ー2. 建設業務
禁止理由: 建設現場における作業には、安全管理や高度な技術が求められるため、通常の派遣形態ではなく、建設業専門の「建設労働者派遣事業」の許可が必要です。
【 該当例 】
土木工事や足場の組立て
建築資材の運搬や整備
建設現場での重機オペレーター
2-3. 港湾運送業務
禁止理由: 港湾の安全確保や労働条件保護の観点から、港湾運送業務への一般派遣は認められていません。港湾運送事業の特例として認可されたケースのみ例外です。
【 該当例 】
港での貨物の積み下ろし
クレーンを用いた船積作業
港湾倉庫での荷さばき作業
2-4.医療関連業務
禁止理由: 医療現場での業務には高度な専門性と緊急対応力が必要であり、派遣労働の形では継続的な教育や責任の所在が不明瞭になるため禁止されています。
【 該当例 】
看護師、臨床検査技師、放射線技師などの医療資格職
医師の診療補助
病棟での患者対応(例外除く)
例外: 育児・産休の代替や紹介予定派遣など、一定条件下では可能。
2-5. 士業(弁護士、税理士など)
禁止理由: 国家資格を要し、独占業務として法律に定められた業務(いわゆる「士業」)は、専門家が個人または事務所の責任で行うもの。派遣形態では責任の所在が曖昧になってしまうため認められていません。
【 該当例 】
弁護士としての法務業務
税理士による申告書作成
社会保険労務士による労務相談
2-6. 労使交渉・協定に関する業務
禁止理由: 労働者派遣法では、派遣社員が労使交渉や協定の締結といった“使用者側の立場”になることを禁止しています。
【 該当例 】
労働組合との交渉
就業規則や賃金制度の見直しに関わる業務
他社員の評価や人事考課
以上が、派遣社員に任せてはいけない「6つの禁止業務」です。これらはどれも法律で明確に禁止されており、違反すると企業にとって大きなリスクを伴います。

3.派遣社員に指示してはいけないこと
派遣社員に業務を依頼する際、業務そのものが禁止されていなくても、「どのように指示するか」に注意しなければなりません。派遣契約には明確な枠組みがあり、それを超えた指示は違法と判断されることがあります。ここでは、派遣社員に対して行ってはいけない3つの代表的な指示について紹介します。
3-1. 契約書に記載のない業務の指示
派遣契約では、業務内容が事前に細かく定められています。派遣社員に新たな業務を任せたい場合は、派遣元と契約内容を見直す必要があります。契約外の業務を派遣先が勝手に指示することは、「偽装請負」と見なされる恐れもあります。
【 NG例 】
「ちょっとこれもついでにやっておいて」と日常的に契約外の業務を指示する
契約にはない部署での勤務を急に命じる
イベント対応など一時的な業務追加を現場の判断で行う
【 対処法 】
業務の変更が必要な場合は、必ず派遣元と協議し、契約を再締結する。
3-2.雇用契約に関する指示
派遣社員の雇用主は「派遣元(派遣会社)」です。したがって、雇用条件や労働時間、休暇の取得などに関して、派遣先が直接指示・変更することはできません。
【 NG例 】
「明日からシフトを変更してもらうから」と一方的に労働時間を変更する
派遣社員に直接「このまま契約更新しないからね」と通告する
派遣元を通さず、休暇取得を拒否または強要する
【 対処法 】
労働条件に関する事項はすべて派遣元を通じて対応する。
3-3.派遣禁止業務への従事の指示
第2章で紹介した「派遣禁止業務」への従事を指示した場合、法令違反となり、罰則の対象になります。本人が了承していても、違反行為となるので注意が必要です。
【 NG例 】
繁忙期に警備の補助を頼む
医療事務の枠で派遣された人に、看護補助を兼務させる
建設現場で書類作成のついでに現場作業を依頼する
【 対処法 】
派遣社員に従事させる業務は、常に契約内容と法令に照らしてチェックすること。
このようなNG指示は、法令違反だけでなく、派遣社員との信頼関係を損なう原因にもなります。企業としても、派遣社員を大切な戦力ととらえ、ルールを守った適切な対応が求められます。
4.違反した場合のリスク
派遣社員に対して法律に反する業務を任せたり、不適切な指示を出したりした場合、派遣先企業は重大なリスクを負うことになります。ここでは、違反行為によって生じる主なリスクを3つの側面から整理して解説します。
4-1.労働者派遣法違反による罰則
派遣契約の違反行為が確認された場合、厚生労働省による是正指導の対象となり、状況によっては以下のような罰則が科されます。
【 主な罰則内容 】
改善命令:是正勧告に応じない場合に発令される行政処分
派遣停止命令:一定期間、対象企業が派遣労働者を受け入れることを禁止
事業許可取消し(派遣元):悪質な場合は派遣元の事業許可自体が取消される
また、刑事罰として「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されることもあります(労働者派遣法第59条)。
4-2. 社会的信用の失墜
法令違反が外部に知られると、企業の社会的信用は一気に低下します。とくに近年では、SNSや口コミサイトを通じて労働問題が広まりやすく、企業イメージに大きな打撃を与える可能性があります。
【 実際にあり得る影響 】
ネットメディアに労務トラブルが掲載される
株主・取引先からの信頼低下
求人応募が減り、採用難に直結する
4-3.派遣社員とのトラブル・損害賠償請求
派遣社員に禁止業務や契約外の指示を行った結果、本人が事故に遭ったり、精神的な苦痛を受けたりした場合、企業は損害賠償責任を問われる可能性があります。
【 考えられる事例 】
建設現場で派遣社員に危険作業をさせ、労災事故が発生
違法な業務指示により精神疾患を発症し、損害賠償請求に発展
契約外の業務で残業がかさみ、未払い賃金の請求が発生
これらは企業にとって「金銭的損失」だけでなく、「法的責任」「内部の職場環境悪化」など、あらゆる面で大きなマイナスをもたらします。
ルールを知らなかった、悪気はなかった――そんな言い訳は通用しません。派遣社員の適切な取り扱いは、企業としてのコンプライアンスの基本であり、守るべき社会的責任です。

5.まとめ|適切な業務指示でトラブル回避を
派遣社員は、現代の多様な働き方を支える大切な戦力です。しかし、法律で明確に定められたルールや制限を無視して運用すれば、企業にとって大きなリスクを招くことになります。本記事で紹介した「派遣社員にさせてはいけない業務」や「指示してはいけない内容」を改めて確認し、今後の実務に活かしましょう。
違法指示・禁止業務は「知らなかった」では済まされない
派遣法は、労働者の安全と適正な雇用を守るために作られた法律です。意図せず違反してしまった場合でも、行政指導や罰則の対象になります。特に以下のような業務には注意が必要です。
- 建設現場での作業
- 医療行為を伴う業務
- 他の社員への人事管理・評価
- 士業の独占業務
- 労使交渉に関わる業務
派遣元との連携がカギ
現場レベルでは「ついでにこれもお願い」といった感覚で指示を出してしまいがちですが、派遣社員の業務範囲は必ず派遣契約に基づいて管理されるべきです。業務内容に変更がある場合は、必ず派遣元と協議し、契約書の再確認・変更を行うことが重要です。
「指示の仕方」も見直すべきポイント
派遣社員に対する指示は、たとえ内容が合法でも、指示の方法や範囲によっては違法となるケースがあります。現場責任者や管理職には、派遣の基本ルールや禁止事項について定期的な研修を行うなど、組織全体でのコンプライアンス意識を高めることが求められます。
法令順守が信頼と生産性を高める
適切な労働環境が整えば、派遣社員も安心して働くことができ、パフォーマンスの向上にもつながります。派遣先企業としての信頼性も高まり、結果として優秀な人材の確保にも好影響をもたらします。
この記事のポイントまとめ
派遣社員に従事させてはいけない「6つの業務」は法律で明確に禁止されている
- 業務の指示内容・方法にも細心の注意が必要
- 派遣元との連携と契約書の内容確認が必須
- 違反すると罰則・信用失墜・損害賠償のリスクがある
- 適切な運用で、派遣社員の力を最大限活かすことができる
最後までお読みいただきありがとうございました。
この内容が、貴社の派遣社員活用に役立つ情報となれば幸いです。もし役立ったと感じたら、ぜひシェアやブックマークもお願いいたします!
お仕事情報のおすすめ記事
-
2025/08/15
信頼を築く!明日から実践できるビジネスマナーの基本
-
2023/02/10
あなたの日常生活を支えるお仕事! 金属加工の仕事内容って?
-
2023/02/24
健康を支える大事な仕事 医療製造の仕事とは?
-
2023/04/28
女性活躍!!品質検査のお仕事とは?